アサリを通じて熊本の干潟を体験!「みすみの干潟で学ぼう!インターン生による研究発表会」を開催しました!
一般社団法人10Toki3Tokiは、「みすみの干潟で学ぼう」の事業運営を担ってきたインターン生による研究発表会を開催しました。子ども達が干潟に降り立ち、アサリの成長観察を通じて、干潟の生態系と環境への関心を高めることを目的としています。
2025.02.10

一般社団法人10Toki3Tokiは、2024年12月3日(火)と2025年1月14日(火)に、「みすみの干潟で学ぼう」の事業運営を担ってきたインターン生による研究発表会を開催いたしました。「みすみの干潟で学ぼう」は、子ども達が直接干潟に降り立ち、アサリの成長を継続して観察するイベント等を運営しながら、干潟の生態系と環境への関心を高めることを目的とした事業です。
このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。
開催概要
干潟とそこに生息する二枚貝には、赤潮・青潮の発生を未然に防ぎ、多様な海の生態系を守る役割があります。しかし熊本県の有明海や八代海では、干潟面積が大幅に縮小し、アサリを始めとした二枚貝の生息数も激減しています。このイベントは、熊本県の「みすみの干潟で学ぼう」事業に携わったインターンの高校生と大学生が、事業の概要や、干潟を用いて研究した内容について、母校で発表しました。
日程
【宇土高校での研究発表会】2024年12月3日 (火)
【東京農業大学での研究発表会】2025年1月14日(火)
開催場所
宇土高校、東京農業大学
参加人数
学生・教員 合計80人ほど
協力団体
宇土高校、東京農業大学
宇土高校での研究発表会:高校生という立場でも干潟再生に貢献できる!
子どもたちが直接干潟に降り立ち、アサリの成長を継続して観察する過程において、干潟の生態系と環境への関心を高めることを目的としている「みすみの干潟で学ぼう」事業。この事業において、イベント企画運営、放流したアサリの生育調査、干潟再生のモデルケースとしてのデータ収集は、全て高校生・大学生のインターン生によって行われています!
まず開催されたのが、地域の高校生による研究発表!地元の高校1年生ながら、イベントの数々の実務をこなし、イベント会場の干潟で研究も進めています。「みすみの干潟で学ぼう」事業について小耳に挟んだこの高校生は、運営団体と直接話して意気投合し、インターン生として事業運営するという大役を担うことになりました。さらには、すでに高校で進めていた竹炭に関する研究と絡めながら、アサリ放流区におけるデータ収集を進め、竹炭が干潟機能を向上させる可能性を見出しました。
発表では、事業のインターン生に至った経緯から、イベントの概要、自身の研究内容とその結果について話しました。竹炭にプランクトンの増加または凝集効果がある可能性については、地域の人々が竹害という環境問題に悩まされていることを踏まえて、学生たちは熱心に聞き入っていました。
しかし、最も学生にとって衝撃的だったのは、「高校生という立場でも干潟再生に貢献できる!」という気付きでした。インターン生として活躍したこの高校生は、事業に携わる中で、子どもたちの干潟の生態系と環境への関心を高め、竹炭の可能性を見出すなど、地域の干潟再生に大きく貢献しています。インターン生になった経緯や仕事の内容について、学生や教員から絶えず質問を受けていました。


東京農業大学の研究発表会:外から見た有明海の干潟と、そこから得た気づき
次に開催されたのが、大学生による発表!この大学生は、普段は首都圏の大学に通っているものの、運営メンバーの誘いを受けて、休学期間を利用して「みすみの干潟で学ぼう」に携わっていました。そして、前々から関心のある世界の食料問題と絡めて、干潟での研究を進めていました。
あまり知られていませんが、二枚貝はとても環境に優しい動物性タンパク源で、今後、牛肉や豚肉、鶏肉に替わるタンパク源になっていくポテンシャルがあります。それも、二枚貝が自然生息できる海域や、二枚貝を養殖できる海域は、まだまだ未活用の場所ばかり!その一つが、有明海や八代海沿岸にたくさん存在する、クルマエビ養殖場の跡地です。「みすみの干潟で学ぼう」は、このようなエビ養殖場跡地を用いて開催されています。
発表では、事業のインターン生に至った経緯、インターン経験、自身の研究内容とその結果について話しました。国土が狭いように思える日本にも、まだまだ未活用の土地がたくさんあります。身近なアサリを始めとした二枚貝が、日本の食料自給率向上はもちろんのこと、世界の食料問題の救世主となりうることに対して、多くの学生の関心を集めていました。

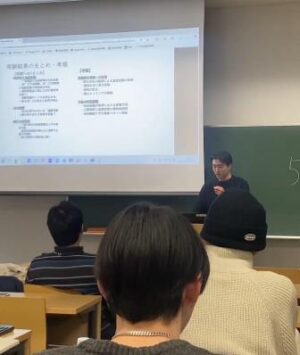
参加した学生・教員からの声
参加した学生
・アサリという普段の生活であまり考えないようなことをテーマにして研究していたからそこが面白かった。
参加した教員
・学生ながら地域に貢献できるような活動を実行できているのは凄いと思った。
イベントレポートは実施事業者からの報告に基づき掲載しています
参加人数:80人

